
担い手3法とは?令和6年の改正内容や目的をわかりやすく解説
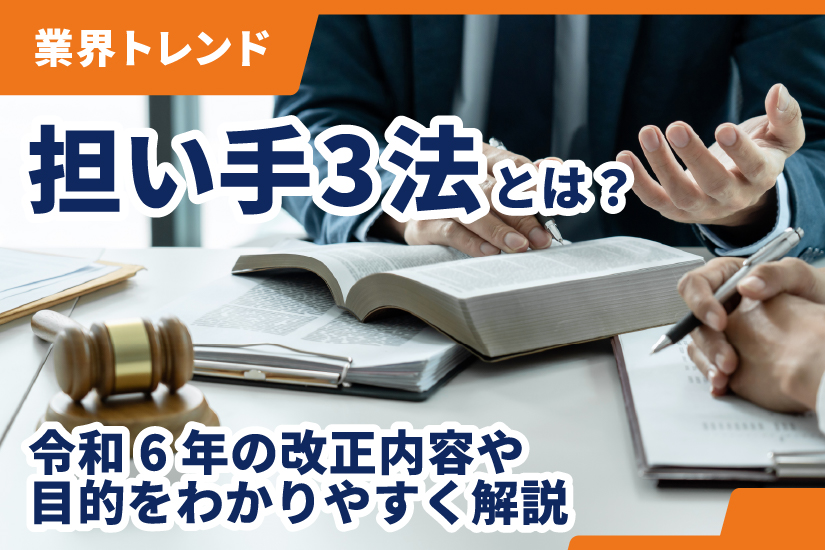
令和6年(2024年)に「担い手3法」の改正が行われ「第3次・担い手3法」が制定されました。
「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」を目的に改正された「第3次・担い手3法」ですが、改正内容を理解したい方もいるのではないでしょうか。
この記事では、令和6年に制定された「第3次・担い手3法」の内容や目的を解説します。担い手3法の改正による建設業界への影響も紹介します。
担い手確保に対する自社の取り組みや継続的に建設事業を行うためにも、ぜひ参考にしてみてください。

【令和6年改正】担い手3法とは
担い手3法とは、以下の3つの法律の総称です。
- 品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)
- 建設業法
- 入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)
担い手3法は、平成26年(2014年)に、品確法・建設業法・入契法の3つの法律が改正されたことを機に、その総称として呼ばれるようになりました。法律のなかでは、以下のようなことが規定されています。
- 予定価格の適正な設定
- 労働条件と労働環境の改善
- ダンピング対策の強化
- 担い手確保 ほか
令和元年(2019年)には、品確法・建設業法・入契法が再び改正され「新・担い手3法」が制定されました。新・担い手3法では、時代の変化による新たな課題を解決するために以下の規定が加えられています。
- 働き方改革の推進
- 生産性向上への取組
- 災害時の緊急対応の充実強化・持続可能な事業環境の確保
- 調査・設計の品質確保
さらに、令和6年(2024年)に「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」を目的として制定されたのが「第3次・担い手3法」です。
【令和6年改正】担い手3法の3本の矢
令和6年に改正された担い手3法には、「3本の矢」と呼ばれる3つの中心的な柱があります。
- 担い手確保
- 生産性向上
- 地域における対応力強化
それぞれ詳しく解説します。
担い手確保
「担い手確保」に規定する具体的な施策は、以下の通りです。
- 処遇改善
- 価格転嫁
- 働き方改革・環境整備
建設業就業者数は、平成9年に685万人とピークを迎えています。しかし、平成22年に504万人まで減少し、令和5年には483万人まで減少しました。
さらに、55歳以上の建設業就業者が36.6%、29歳以下は11.6%です。建設業就業者の高齢化が進み、技術継承が課題となっています。
建設業界の人材不足を解決するためには、業界全体で労働環境の整備に努めることが重要です。産業別年間出勤日数を見ると、建設業界の年間出勤日数は全産業と比べて11日多いことがわかります。産業別年間実労働時間は、全産業よりも62時間多くなっています。
国土交通省は週休2日制を推進し、休日を確保するための取り組みを進めています。しかし、すべての建設現場で週休2日を実現できているわけではありません。技術者も技能者のいずれにおいても、4週8休(週休2日)以上を確保できている割合が2割程度で、多くの場合は4週6休となっています。
若手人材や外国人が希望を持って仕事ができる建設業界にするためには、適正な工期を設定したり長時間労働を是正したりするなど、週休2日を実現するための取り組みを進めることが重要です。
参考:国土交通省|改正建設業法について~改正建設業法による価格転嫁・ICT活用・技術者専任合理化を中心に~令和6年12月「01.建設業を取り巻く現状 (1)(4)建設業における働き方の現状
参考:国土交通省|改正建設業法について~改正建設業法による価格転嫁・ICT活用・技術者専任合理化を中心に~令和6年12月「01.建設業を取り巻く現状 (1)建設業就業者の現状」
生産性向上
「生産性向上」に規定する具体的な施策は、以下の通りです。
- ICTの活用
- 新技術の開発
- 現場技術者の専任の合理化
国土交通省は「i-Construction」と呼ばれる生産性向上施策を進めてきました。国土交通省|i-Constructionの推進「i-Construction トップランナー施策」によれば、以下の3つを施策として掲げています。
- ICTの全面的な活用(ICT土工)
- 全体最適の導入(コンクリート工の規格の標準化等)
- 施工時期の平準化
ICTの全面的な活用(ICT施工)には、ドローンを活用した3次元測量や3次元測量点群データを活用した設計図面の作成などがあり、建設現場にICTを導入することで生産性向上の実現が期待できます。
さらに、令和6年4月に「i-Construction2.0」が公表され、省人化対策や自動化の施策が定められました。業務の一部にICTを活用するなど、生産性向上につながる対策を実施することが重要です。
また、現場技術者(主任技術者や監理技術者)の専任の合理化として、情報通信機器を活用して遠隔で現場の状況を確認できることを条件に、現場の兼任が可能となりました。
ただし、主任技術者や監理技術者として業務をするためには、所定の実務経験を持つか国家資格を保有する必要があります。現場技術者の資格取得を支援することも重要です。
参照:国土交通省|【建設業法】現場技術者の専任合理化(R6.12.13施行)
地域における対応力強化
「地域における対応力強化」に規定する具体的な施策は、以下の通りです。
- 地域建設業等の維持
- 公共工事等の発注体制の強化
地域建設業等の維持として、地域の建設業が継続して事業をするために、発注者は適切な入札条件で発注する必要があると定めています。これは、地域建設業者の経営安定化を図り、その減少に歯止めをかける狙いがあります。
また、自然災害による被害が生じた場合は、一刻も早い復旧・復興が重要です。技術力のある民間事業者と地域の民間事業者が連携して復旧・復興に対応できるように、災害対応力を強化すると定められています。
さらに、公共工事等の発注体制の強化として、発注職員の育成や発注事務の助言など発注者への支援を充実することも定められています。

担い手3法の改正による建設業界への影響
担い手3法の改正による建設業界への影響は、以下の通りです。
労働者の処遇改善につながる
担い手3法が改正されたことで、労働者の処遇改善が期待できます。
国土交通省の中央建設業審議会は、労務費の基準を作成し勧告を行うことで、労務費の確保に関する取り組みを実施しています。注文者が、その地位を不当に利用して通常よりも著しく低い額で請負契約を締結することなどが、担い手3法の改正により禁止となりました。
能力に応じた適切な処遇改善を実施することで、建設業界の担い手確保の観点からプラスに働くと予想できます。
価格高騰による労務費の上昇に対応できる
担い手3法の改正により、価格高騰による労務費の上昇に対応できるようになりました。原材料や輸送コストの高騰にともない資材価格が高騰しています。
担い手3法の改正では、以下のように工事の契約前と契約後で価格転嫁のルールが決められました。
工事の契約前と契約後の価格転嫁のルール
契約前 |
|
契約後 |
|
資材価格が高騰すると、労務費へのしわ寄せが生じるリスクも高まります。担い手3法の改正で価格転嫁のルールが定められたため、資材価格の高騰による労務費のしわ寄せの防止につながったといえます。
働き方改革の推進が実現する
担い手3法の改正は、働き方改革の推進に対して大きな影響を与えます。建設業界の年間実労働時間は、全産業と比べると62時間長いことがわかっています。
建設業界では、2024年度から時間外労働の罰則付き上限規制が適用されました。担い手3法では、担い手確保を目的として「働き方改革・環境整備」を定めているため、建設業界の働き方改革が、より一層加速することが期待されます。
参照:厚生労働省|建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
まとめ
この記事では、令和6年に改正された担い手3法の改正内容や目的を解説しました。
令和6年に「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」を目的として制定された「第3次・担い手3法」。担い手3法の改正により「処遇改善」「働き方改革」「生産性向上」に対して、総合的に取り組む必要があります。
建設業界の労働環境を改善することで、新4K(給与が良い・休日が取れる・希望が持てる・かっこいい)の実現が期待できます。新4Kを実現できれば、建設業界の担い手確保にもつながるでしょう。
担い手3法の改正で定められた内容をふまえ、自社で対策に取り組むことが大切です。この記事を参考に、担い手確保に関する自社の取り組みについて考えてみてはいかがでしょうか。

