
一人親方の労災保険料はどう決まる?「給付基礎日額」で変わる保険料とその選び方
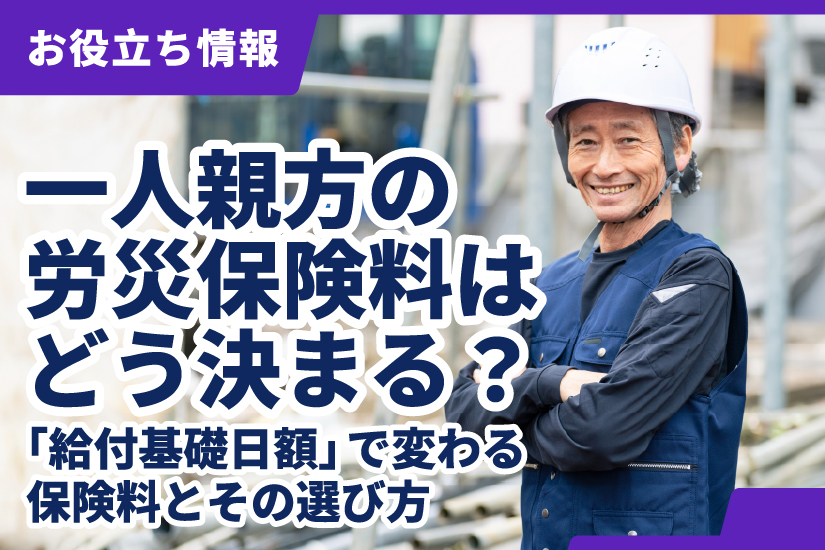
一人親方にとって、労働者災害補償保険(以下、労災保険)への加入は万が一の備えとしてだけではなく、信頼される仕事人としての証でもあります。事故やケガのリスクに対してみずから備えなければならない一人親方は、労災保険の「特別加入制度」によって、公的な補償を受けられます。
とくに近年では、元請企業が加入を条件とするケースも増えており、労災保険に加入しているかどうかが仕事の受注に関わることもあります。安心して現場に立ち、信頼される仕事を続けるためにも、特別加入制度の正しい理解と加入は欠かせません。

一人親方の労災保険料はどう決まる?仕組みと計算式
一人親方の労災保険料は、「給付基礎日額」と呼ばれる1日あたりの補償額に基づいて決まります。この金額は3,500円から25,000円までの16段階で自由に選ぶことができ、選んだ金額に業種ごとの保険料率をかけて保険料が算出されます。
- 給付基礎日額(3,500円〜25,000円) × 365日 × 業種ごとの保険料率 = 年間保険料
給付基礎日額は、補償額だけではなく保険料にも大きく関わるため、ご自身の収入やリスクに合った金額を設定することが大切です。
給付基礎日額は、保険料と給付額を左右する重要な選択肢
給付基礎日額を高く設定すると、手厚い補償が受けられる一方で、保険料の負担も大きくなります。逆に、低く設定すれば保険料は安くなりますが、補償額も抑えられてしまいます。
設定ごとのメリットと注意点は以下のとおりです:
- 高額設定:補償は充実、保険料は高め
- 低額設定:保険料は安いが、補償が足りないリスクも
- 収入や家族構成に応じたバランスが重要
給付基礎日額は、ご自身で調整できる数少ない要素のひとつです。しっかり比較して選びましょう。
一人親方の労災保険料計算例|収入に応じたシミュレーション
給付基礎日額に応じて、年間保険料は大きく変わります。建設業・一人親方の保険料率(17/1,000=1.7%)をもとに計算した例を見てみましょう。
- 給付基礎日額7,000円 → 年間保険料 約43,435円
- 給付基礎日額12,000円 → 年間保険料 約74,460円
- 給付基礎日額20,000円 → 年間保険料 約124,100円
ご自身の収入や貯蓄、生活費、仕事のリスクをふまえて、無理のない範囲で適切な給付基礎日額を選びましょう。

一人親方こそ、労災保険に加入すべき理由
たった一度の転落や道具の落下が、仕事も生活も奪う──これは決して大げさではありません。実際に高所から転落し、長期の入院とリハビリを経ても仕事に復帰できず、廃業に追い込まれた一人親方もいます。労災保険に未加入だったため、治療費や生活費はすべて自己負担となりました。
2023年に労災事故を経験した建設業の一人親方106人への調査では、25%が保険未加入で、うち約4割が「休業補償を受けられなかった」と回答しています。事故後に加入の重要性を感じた方は83.3%にものぼり、「事故はいつ起きるかわからない」との声が多く寄せられました。
出典:一般社団法人労災センター|労災事故経験のある一人親方、事故時75.0%が労災保険に特別加入(PR TIMES、2023年5月12日)
労災保険に加入することは、備えと信頼の両立につながる
特別加入制度によって、ケガや病気で働けなくなった場合の休業補償、障害補償、万が一の際の遺族補償が受けられます。現場で常にリスクにさらされる一人親方にとって、万が一に備える制度は重要なライフラインです。
また、加入していることで元請企業との契約がスムーズになり、受注できる案件の幅も広がります。さらに、現場に入る際には安全書類として加入証明書の提出が求められる場面も多く、作業開始を円滑にする役割も果たします。
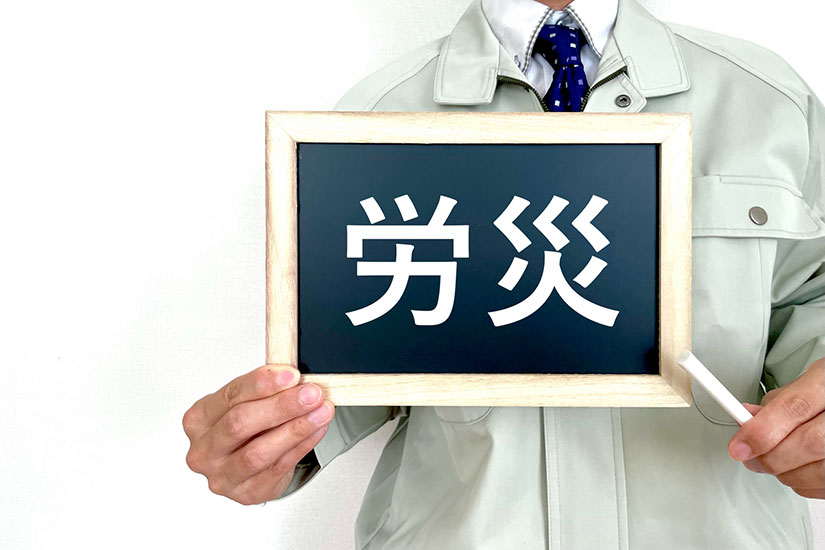
「自分を守る保険」であると同時に、「信頼される事業者」としての証明にもなる──それが労災保険の特別加入制度です。どの給付基礎日額を選ぶべきか?リスク許容度で考える
給付基礎日額は、一人親方がご自身で自由に設定できる、数少ない保険設計のポイントです。ただし、「給付基礎日額を高くすれば補償も大きくなるけど、保険料も上がる。どこまでが適正なのか?」というのは、多くの方が感じる疑問ではないでしょうか。選び方に正解はありませんが、以下のような視点でバランスを取ることが大切です。
無収入の期間をどう乗り切る?生活費から給付基礎日額を考える
給付基礎日額は、ケガや病気で働けなくなったときに支給される休業補償の金額を決める重要な要素です。
ここで考えたいのは、「もし収入がゼロになったら、最低限どれくらい毎月必要か?」という点です。次のような支出をもとに計算してみましょう。
- 食費や光熱費、通信費などの変動費
- 家賃や住宅ローン、保険料などの固定費
- 子どもがいる場合の保育料や学費
- 入院や通院にかかる雑費・交通費
給付基礎日額は、年度の途中で変更することは原則できません。変更したい場合は、更新時(通常は年度末)に申請する必要があります。そのため、設定時には「いざというときに必要な補償額に少し余裕を持たせた水準」を選んでおくと安心です。
※補足:年度の途中であっても、災害発生前であれば給付基礎日額を変更できる場合があります。
過剰な保障は逆効果?保険料とのバランスを取る
「高いほうが安心だから」と最大限の補償を選んでしまうと、保険料が思った以上に高額になり、支払いが苦しくなってしまうケースもあります。保険は「入って終わり」ではなく、続けてこそ意味がある制度です。
たとえば、給付基礎日額を20,000円に設定すると、年間保険料は124,100円にものぼります。これが毎年の固定コストになると考えると、無理のない支払い水準を見極める必要があります。
選ぶときのポイントは以下のとおりです:
- 必要以上に高額な給付基礎日額は避ける
- 「最悪の1か月〜3か月」をカバーできる程度でOK
- 生活費の7〜8割を補償できれば安心感は高い
ご自身の収入や貯蓄、ケガのリスク、家族構成を踏まえて、「無理なく続けられる」金額を設定することが何より重要です。
労災保険はコストではなく「信用への投資」
一人親方にとって、労災保険への加入は単なる「コスト」ではありません。現場での安全意識の高さを証明し、元請企業や顧客からの信頼を得るための「投資」ともいえます。近年は安全管理を重視する傾向が強まり、労災保険未加入者との契約を避ける企業も増えています。加入証明書の提示を求められる場面も少なくありません。
つまり、保険に入っていることで新しい仕事の機会が広がり、結果的に安定した収入にもつながっていくのです。安心して仕事に取り組み、信頼される職人として活躍するために、労災保険の存在は大きな意味を持ちます。
まとめ|ご自身の働き方とご家族の安心を守る最適な選択を
労災保険は、強制ではないからこそ「自分の身は自分で守る」意識が必要です。
保険料を単なるコストと捉えるのではなく、ケガや病気による突然の収入減に備える「安心の土台」と考えてみてください。
一人親方として長く働き続けるためにも、そして大切なご家族の生活を守るためにも、労災保険の特別加入制度は強い味方になります。
今の自分に必要な備えとは何か、立ち止まって考えるきっかけとして、ぜひ前向きに検討してみてください。

