
指定建築材料一覧|JIS適合品と大臣認定の違い、材料証明書の取得方法を解説
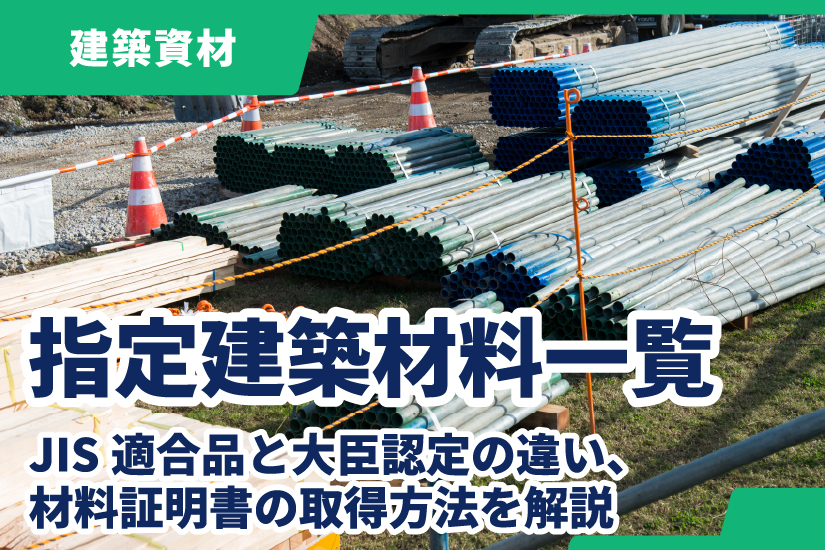
入札する工事において、指定建築材料を使用することもあるでしょう。しかし、指定建築材料とは何かがわからないという方もいるかもしれません。
指定建築材料を調べるうちに、JIS適合品や大臣認定などの言葉も出てくるため、それぞれを混同しやすいのも特徴です。
この記事では、23種類の指定建築材料を紹介します。JIS適合品と大臣認定の違い、材料証明書の取得方法も解説するので、必要な材料証明書を明確にするためにも参考にしてみてください。

指定建築材料とは
建築基準法では、指定建築材料について以下の通り記述があります。
(建築材料の品質)
第三十七条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格又は日本農林規格に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの
引用:建築基準法|第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(建築材料の品質)
指定建築材料の中には、高力ボルトや免震材料などがあります。指定建築材料とは、国土交通大臣が定める木材・鋼材・コンクリート・その他の建築材料のことで、品質や強度などが安定的に確保されることが求められます。
指定建築材料を建築物の性能を確保する上で重要な部分に使用する場合は、原則としてJIS/JASの適合または大臣認定の取得が必要です。国土交通大臣の認定を受ける際は、性能評価と認定を受けなければなりません。
参照:国土交通省|建築基準法における新材料・新技術への対応 令和5年1月27日
参照:国土交通省|新材料・新工法を用いて建築物を建てたいとお考えの方へ
指定建築材料の種類【一覧】
指定建築材料には、以下の23種類があります。
指定建築材料
材料区分 | 代表例 | JIS/JASの有無 | 大臣認定の要否 |
|---|---|---|---|
構造用鋼材及び鋳鋼 | ・H形鋼 ・鋼矢板 | 有 | 否 |
高力ボルト及びボルト | ・アンカー用ボルト ・ナット ・座金 | 有 | 否 |
構造用ケーブル | ワイヤーロープ | 有 | 否 |
鉄筋 | ・異形棒鋼 ・コンクリート用棒鋼 | 有 | 否 |
溶接材料(炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウム合金材の溶接) | ・被覆アーク溶接棒 ・ガスシールドアーク溶接フラックス入りワイヤ | 有 | 否 |
ターンバックル | 建築物用ターンバックル | 有 | 否 |
コンクリート | ・普通ポルトランドセメントと低熱ポルトランドセメントを混合使用し たコンクリート ・高強度コンクリート | 有 | 否 |
コンクリートブロック | 建築用コンクリートブロック | 有 | 否 |
免震材料 | ・ゴム支承 ・すべり支承 | 無 | 要 |
木質接着成形軸材料 | 木材の単板を積層接着又は木材の小片を集成接着した軸材 | 有 | 否 |
木質複合軸材料 | 木材を接着剤によりI形・角形の断面形状に複合構成した軸材 | 有 | 否 |
木質断熱複合パネル | 平板状の有機発泡剤の両面に構造用合板を接着剤により複合構成した枠組みがないパネル | 有 | 否 |
木質接着複合パネル | 木材を使用した枠組に構造用合板を接着剤により複合構成したパネル | 有 | 否 |
タッピンねじその他これに類するもの | タッピング1種〜4種 | 有 | 否 |
打込み鋲 | 丸頭パーカー鋲 | 有 | 否 |
アルミニウム合金材 | アルミニウムコイル | 有 | 否 |
トラス用機械式継手 | 溶接が不要な機械式継手 | 無 | 要 |
膜材料・テント倉庫用膜材料及び膜構造用フィルム | A種・B種・C種・テント倉庫用・膜構造用フィルム | 無 | 要 |
セラミックメーソンリーユニット | セラミックブロック | 有 | 否 |
石綿飛散防止剤 | アスベスト粉じん飛散防止処理剤 | 無 | 要 |
緊張材 | ・PC鋼棒 ・PC鋼より線 | 有 | 否 |
軽量気泡コンクリートパネル | ・厚形パネル ・薄形パネル ・一般パネル | 有 | 否 |
直交集成板 | ・スギ ・ヒノキ | 有 | 否 |
参照:国土交通省|○建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件


【指定建築材料】JIS適合品と大臣認定の違い
指定建築材料と関連性が高いのが、JIS適合品と大臣認定の2つです。
JIS適合品と大臣認定は混同しやすいため、それぞれについて押さえておきましょう。
JIS適合品と大臣認定の違い
JIS適合品 | 「日本産業規格」と呼ばれる産業標準化法に基づいて制定される鉱工業品等の国家規格 |
|---|---|
大臣認定 | さまざまな建築材料や構造方法などを導入するため、その性能が建築基準法に適合していることを国土交通大臣が認定する制度 |
指定建築材料の中にはJIS適合品と不適合品がありますが、JIS適合品ではない指定建築材料は、大臣認定を受けなければなりません。ただし、免震材料や膜材料にはJIS適合品がないため、すべて大臣認定を受ける必要があります。
大臣認定を受けるためには、以下の2つのステップを実施します。
大臣認定を受けるための2つのステップ
性能評価 | 申請のあった構造方法などの性能を確かめるために技術評価を実施する ※技術評価は、国土交通大臣の指定を受けた指定性能評価機関にて行う |
|---|---|
認定 | 指定性能評価機関から交付された性能評価書に基づき国土交通省が審査・認定する |
材料証明書を取得する方法
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」には、JIS/JAS適合品以外の材料の品質を証明するためには、材料証明書を監督職員に提出しなければならないと記載されています。
ここでは、材料証明書を取得する方法を解説します。
設計仕様書通りに使用する材料を確認する
設計仕様書を見て、どのような材料が使用されているかを確認しましょう。
JIS/JAS適合品で、あらかじめ監督職員の承諾を受けていない場合は、材料証明書を提出する必要があります。
まずは、必要となる材料証明書を明確にすることが大切です。
メーカーなどから材料証明書を取得する
使用する材料のメーカーや指定の商社などに問い合わせ、材料証明書を取得しましょう。
材料証明書を入手するまでに時間がかかることもあるため、早めにメーカーなどに依頼すると安心です。
元請に提出するものだけでなく、自社で保管する材料証明書も取得すると良いでしょう。
取得した材料証明書は保管する
材料証明書を入手した後は、工事が完了するまで保管しておきましょう。
材料証明書の明確な保管期間は決まっていませんが、青色申告法人は帳簿書類を7年間保存しなければならないと、法人税法施行規則で決まっています。
契約書・送り状・領収書・見積書と同じように、材料証明書も保管しておきましょう。
参照:法人税法施行規則|第四章 青色申告(帳簿書類の整理保存)第五十九条
参照:国土交通省|公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版
まとめ
今回は、指定建築材料の種類をはじめ、JIS適合品と大臣認定の違いや材料証明書の取得方法について解説しました。この記事を通して、工事入札の際に必要な材料証明書について整理できたことでしょう。
指定建築材料には、JIS適合品と不適合品があります。JIS適合品ではない指定建築材料は、大臣認定を受ける必要があります。また、材料の品質を証明するために、監督職員に材料証明書を提出しなければなりません。
信頼できる業者を見つけるためには、施工業者を結ぶマッチングサービス「スケッタブル」の活用がおすすめです。
「スケッタブル」では、防水材や塗装材などの建築資材の調達も行っていますので、材料証明書の準備までスムーズに進められるでしょう。
効率良く資材を調達したい方は、ぜひスケッタブルの活用もご検討ください。

