
【2025年6月から義務化】今日からできる建設業の熱中症対策のポイント
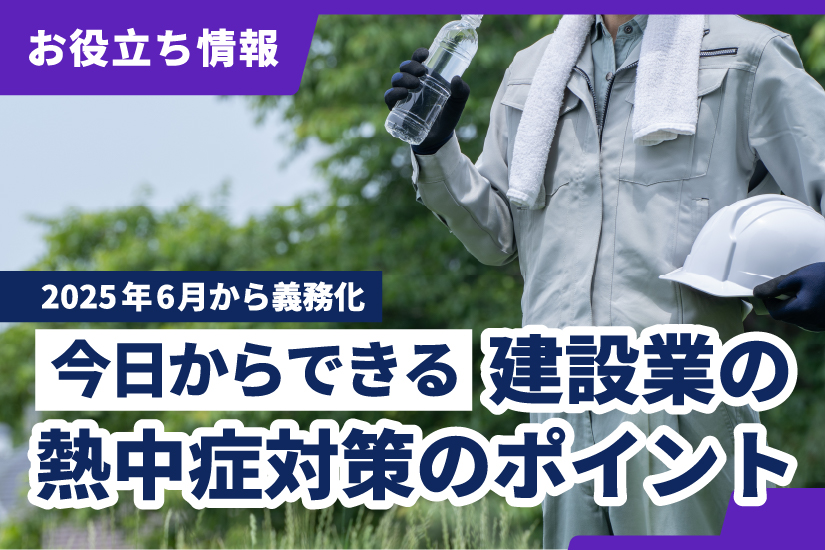
建設業では他の業種に比べ熱中症による事故が多く、熱中症対策の強化が急務となっています。2025年6月からは建設現場での熱中症対策が法律で義務化され、現場で働く人の安全確保がこれまで以上に重要になりました。
本記事では、建設業で熱中症が発生しやすい背景や、事業者が遵守すべき法令のポイント、そして現場で今すぐ実践できる具体策まで徹底解説します。

建設現場で熱中症が起きる原因とは?
建設現場は、直射日光が照りつける屋外での作業に加え、重い物を運ぶことによる体への負担、ヘルメットや作業服による熱のこもりが重なります。
さらに、長時間の連続作業による疲労が体温調節の機能を妨げ、熱中症の発症を引き起こします。
実際に令和5年に職場で発生した熱中症による死傷者は1,106人。そのうち約4割が建設業と製造業で発生し、建設業では12人が命を落としました。*1
現場の過酷な労働環境が、深刻な健康被害を招いている現実がうかがえます。
建設業の熱中症対策が義務化!事業者が守るべき法令のポイント
労働安全衛生法では、労働者に対して飲料水や塩分を用意することが事業者の責務とされています。
近年の酷暑や熱中症による死傷者数の増加を受け、これまで自主的な取り組みに委ねられていた熱中症対策が、法的に義務づけられるようになりました。
2025年6月1日からは改正労働安全衛生規則が施行され、事業者には体制整備や労働者への教育など、具体的な対策の実施が求められています。
企業規模を問わず、すべての建設現場での確実な実施が必要です。
事業者に求められる具体的な措置とは?
WBGTが28度以上または気温31度以上の環境下で行われる作業が、連続して1時間以上または1日4時間を超えると見込まれる場合、熱中症対策の義務が適用されます。*2
- 熱中症の兆候を素早く発見できるよう現場での監視体制の整備
- 作業員に症状が出た際、重症化を防ぐための適切な応急処置手順の策
- 上記の体制や手順について全作業者への周知・教育
違反した場合の罰則規定
事業者が労働安全衛生規則の熱中症対策の義務に違反した場合、法的な制裁の対象となります。
具体的には、労働安全衛生法違反により6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
また、熱中症が原因で労働者に死亡事故が発生した際には、業務上過失致死など刑事責任を問われることも免れません。
悪質な違反と判断された場合、行政から事業停止命令など厳しい処分が下されるというリスクも念頭に置くべきです。
建設現場ですぐに実践できる熱中症対策リスト

ここからは、建設現場ですぐに実践できる熱中症対策の方法を紹介します。現場の状況に応じて取り入れ、安全で健康な職場環境づくりにお役立てください。
1. 高温を避けるための作業環境づくりをする
暑さ対策は日陰や空調だけでなく、風通しや時間帯に配慮しましょう。
以下の工夫を組み合わせて、安全な環境を整えてください。
- テントやシートで日陰を作り、打ち水をして地面からの照り返しを抑える
- 作業開始前に天気予報やWBGTを確認し、気温が高くなる日は作業時間の変更や日程の見直しをする
- 扇風機やミストファンを設置し、現場内の空気を循環させて熱気を逃がす
- エアコン完備の休憩所や身体を冷やせるスペースを設置し、誰でも自由に利用できるよう案内する
日差しの向きや風の通り方の違いで暑さのたまりやすい場所は変化します。
「どこが一番暑いか」は日によって変わるので、定期的に温度を測って対策を見直しましょう。
2. 気温に合わせて作業計画と休憩を見直す
時間割通りの作業にこだわらず、その日の暑さに応じて柔軟に動くことが熱中症予防のカギです。
以下の工夫を取り入れ、無理のない作業環境を整えましょう。
- 日中の作業を控え、早朝や夕方の涼しい時間帯に作業を移す
- 休憩時間はあらかじめスケジュールに組み込み、現場全体で確実に実施する
- 経験の浅い人や久しぶりに現場に戻る人には、暑さに慣れるための期間を作り、最初の数日は軽作業から段階的に慣れてもらう
- 連日長時間の作業や残業を避け、十分な休養が取れるように配慮する
休憩は疲れてから取るのでは遅く、決めた時間より早めに取るくらいが効果的です。
体温が上がりきる前に休むことで、体への負担を減らし、回復もしやすくなります。
3. 空調服や冷却グッズで体温の上昇を防ぐ
現場ではただ冷やすだけでなく、作業者に合った冷却方法を選ぶことが安全性を高めるうえで大切です。
以下の工夫を取り入れ、体温の上昇を防ぐ装備を整えましょう。
- 通気性と吸汗性に優れた作業着を選び、体に熱がこもらない工夫をする
- ファン付きの作業着を導入し、衣服内の熱気を風で逃がして体温の上昇を抑える
- ネッククーラー、冷却タオル、冷却剤入りベスト、携帯用の氷嚢などを準備し、体の表面をこまめに冷やす
- ヘルメットや防護服には遮熱素材や冷却パッド付きの製品を取り入れ、頭部や胴体の温度上昇を防ぐ
体を冷やしすぎると血流が悪くなったり、体温調節が乱れたりすることで、作業中にだるさを感じる人もいます。
それぞれに合った冷却グッズを選び、状況に応じて使い分けることがポイントです。
4. 水分と塩分の補給を習慣化し、脱水を防ぐ
暑いときだけ飲むのでは遅く、体が欲しがる前に補給する習慣をつくることが脱水を防ぐポイントです。
次の工夫を取り入れ、こまめな補給を意識しましょう。
- 喉の渇きを感じていなくても、15~20分ごとに少量ずつ水分を取る
- 発汗で塩分やミネラルも失われるため、スポーツドリンクや塩飴などで電解質もこまめに補給する
- 冷たい飲み物やシャーベット状に凍らせたアイススラリー飲料を活用して、体の内側からも冷やす
- 定時の休憩を義務づけ、全員が体を冷やせる時間を確保する
気温が低めの日でも湿度が高いと汗は出やすいので、「今日はそんなに暑くない」は油断につながります。こまめな水分補給を忘れずに心がけましょう。
5. 毎日の体調確認と健康管理を徹底する
体調不良は本人も気づかないうちに始まっていることが多いため、日々の小さな変化に気づける仕組みづくりが大切です。
以下の取り組みを通じて、体調変化に素早く対応できる体制を整えましょう。
- 定期健診や問診結果を活用して、高血圧や肥満などリスクが高い人を把握しておく
- 作業中はリーダーが巡回し、一人ひとりの顔色や発汗量に異変がないか目を配る
- 作業員同士でバディ制・チーム制を取り入れ、体調を相互に確認する
- 作業前に体調チェックシートを記入し、体温や睡眠時間、体調を申告する習慣をつける
体調不良を申告しやすい雰囲気がないと我慢する人が出やすくなるので、「無理せず言っていい」という空気づくりが重要です。
6. 作業前に熱中症の知識と予防方法を共有する
熱中症対策では、知っているつもりが最も危険です。基本を繰り返し伝えることで、「分かっている」を「できている」に変えることが現場の安全につながります。
以下の取り組みを行い、予防意識を育てましょう。
- 夏本番前に安全衛生教育を実施し、熱中症の正しい知識と予防策を全員で共有する
- 朝礼やミーティングで事例や他社の取り組みを紹介し、熱中症の危険性と予防法を具体的に伝える
- 日常的にコミュニケーションを取り、体調不良をすぐに報告・相談できる職場風土をつくる
一方的に説明するだけでなく、「実際に自分がヒヤッとした体験」を共有することで現場全体に危機感が伝わりやすくなります。

熱中症の症状が出たときの応急対応の手順
万全を期しても、現場で誰かが熱中症になる可能性はゼロではありません。
作業中にめまい・吐き気・異常な発汗などの症状が出た場合、以下の応急措置を行いましょう。*3
- 本人を日陰や冷房の効いた場所へ避難させる
- ヘルメットや安全帯を外し、衣服を緩めて体熱を逃しやすくし、首筋・脇の下・太ももの付け根などを中心に氷嚢や保冷剤で集中的に冷やす
- 水分を自力で摂取できる場合は、経口補水液などで水分と塩分を補給する
呼びかけに応答しない場合は、ためらわずに119番通報し、医療機関の指示を仰ぎます。
救急隊や医師には、現場の気温・作業内容・行った処置・症状の発現からの経過時間などを伝えましょう。
建設現場の熱中症対策は今すぐ行動を
建設現場での熱中症対策は、働く人の命を守るために欠かせない最優先の取り組みです。
法令による義務化も進む中、本記事で紹介した対策をぜひ今日から現場で実践してみてください。
「安全はすべてに優先する」という意識を職場全体で共有し、誰もが安心して働ける環境づくりを進めましょう。
社員の安全と健康を守ることは、結果として現場の生産性向上や企業への信頼にもつながります。
出典:
*1 令和5年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します|厚生労働省

