
【2025年施行】建設業法改正に備える|見積り・契約・現場管理の新ルール対応完全ガイド
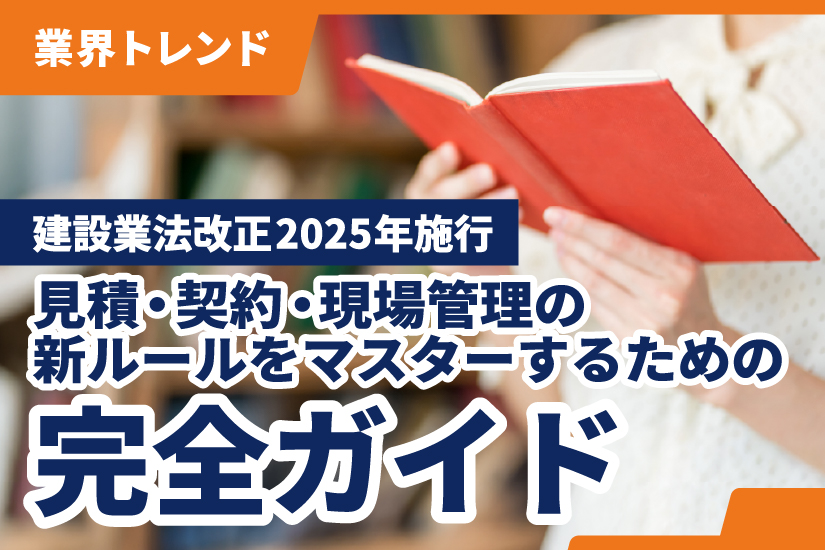
2024年から段階的に施行されている建設業法改正は、見積り、契約、現場管理の常識を抜本的に更新します。背景にあるのは、処遇改善・資材高騰対策・働き方改革の三本柱。施工会社と発注者は新ルールへの適合が不可欠です。
この記事では、中小〜中堅の施工会社経営層や発注企業が着手すべき実務対応を整理し、変化を自社の競争力向上につなげる道筋を示します。

2025年建設業法改正の要点
今回の建設業法改正は、業界が抱える課題を解決し、持続可能な発展を目指すための重要な一歩です。
改正の核となるのは「処遇改善」「資材高騰対策」「働き方改革」の三本柱です。これに基づき、2024年9月から見積もりや契約に関する新基準が、同年12月からは現場管理の新基準が順次スタートしており、2025年末には全面施行が予定されています。
特に、適正な労務費の確保や、原価を割る不当な契約、著しく短い工期の契約が禁止される点は、すべての事業者が必ず対応すべき重要なポイントといえるでしょう。
出典:国土交通省|建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について
2025年改正の三本柱—業界の未来を左右するポイント
2025年の建設業法改正は、3つの重要な柱で構成されており、これらは業界の未来を明るく照らすための指針となります。
処遇改善
賃金水準や職場環境の底上げを通じて、人材定着と採用力の強化を図ります。自社の賃金・手当・安全衛生の実態を点検し、改善計画に反映することが鍵です。
資材高騰対策
資材価格の上振れに耐える契約・見積りの仕組みを整えます。価格変動条項の活用や調達の安定化で、収益の変動を抑えられます。
働き方改革
長時間労働の是正と生産性向上を両輪で進めます。工期・要員計画の適正化、デジタル活用による段取り改善で、ワークライフバランスと品質を両立させましょう。
段階的な施行スケジュール—押さえるべき重要日程
建設業法改正は段階的に施行されるため、施行日程に合わせて順次対応を進める必要があります。
- 2024年9月1日
見積り・契約関連の新基準が施行済み。この日以降の案件は新基準フローで統一しておくと齟齬が出ません。 - 2024年12月13日
現場管理の新基準が施行済み。現場ルール・帳票・教育をこの日までに切り替える前提で整理を。 - 2025年末(予定)
全面施行。未対応領域の洗い出しと最終是正を完了させるタイミングです。
改正内容の詳細解説—具体的にどう変わるのか
2025年の改正では、主に以下の7項目が実務に影響します。それぞれの概要と具体的な運用例を確認し、社内対応の参考にしてください。
1. 労務費基準の新設
新しい労務費基準に基づき、作業員の賃金や福利厚生を適正に管理する必要があります。低賃金による人材流出を防ぎ、技術力を維持する狙いがあります。
具体例
- 技能者の資格手当や交通費を見直し、基準を満たすよう月給を引き上げる
- 協力会社にも労務費基準に沿った給与明細の提出を求め、下請けも含めた賃金適正化を実施
2. 原価割れ契約の禁止
材料費・労務費などを下回る価格で契約することが禁止され、適正利潤を確保した契約が義務化されます。無理なコスト削減を防ぎ、品質と安全の確保につなげます。
具体例
- 鋼材価格が契約時より10%高騰した場合、契約書の価格変動条項に基づき追加精算する
- 見積り時に材料単価の根拠資料(仕入れ先の見積り書等)を添付し、発注者と共有
3. 短工期契約の禁止
過度に短い工期での契約を防ぎ、安全や品質、作業員の健康を守ります。工期の適正化により、突貫作業による事故や品質低下のリスクを減らすことができます。
具体例
- 工期2週間の依頼を、工程分析の結果4週間が必要と判断し、発注者と再協議して延長
- 台風シーズンの屋外工事では、天候による遅延リスクを事前に契約書へ盛り込み、無理な短縮を避ける
4. ICT活用専任者の合理化
ICTの活用により遠隔での管理が可能になるなど、特定の条件下で主任技術者や監理技術者が複数の現場を兼任できるよう要件が緩和され、効率的な人材配置が可能になります。
具体例
- 現場監督がタブレットで施工写真をクラウド共有し、遠隔地の本社技術者が即時チェック
- 複数現場を1人のICT担当がリモート支援し、3D測量や進捗確認を一括管理
5. リスク情報提供義務の強化
施工業者は工事に伴う危険や不確実性を、契約前後に発注者へ明確に伝える義務があります。事前の合意形成が進み、契約後のトラブルを防ぎます。
具体例
- 地盤調査で軟弱層が判明した場合、基礎補強が必要なことを契約書に明記
- 高所作業を伴う工事で、落下防止設備や作業制限時間を仕様書に記載
6. 技術者配置要件の強化
契約内容や工事規模に応じた適正な技術者を現場に配置する義務が強化されます。必要な資格や経験を持つ人材を配置しない場合、契約違反となる可能性があります。
具体例
- 1級施工管理技士が必要な現場に、同資格を持つ社員を常駐させる
- 技術者が不在となる期間には、代替要員の資格や業務範囲を事前に発注者へ提示
7. 社会保険の適用範囲拡大
すべての建設業者に社会保険加入義務が強化されます。未加入の場合は元請からの受注制限や公共工事の入札資格停止につながる可能性があります。
具体例
- 新規契約時に協力会社の社会保険加入証明書を確認し、未加入業者とは契約しないルールを策定
- 社員・常用下請労働者全員の加入状況を年1回チェックし、更新手続きを一括管理

見積り・契約・現場管理への影響—改正で何が変わる?

改正が見積り・契約・現場管理に与える影響は大きく、原価割れ契約禁止や短工期契約禁止など、新たなルールに基づく契約管理が必要です。
見積り・契約—従来の常識からのアップデート
改正により、見積りや契約書は根拠の可視化と適正工期が前提になります。特に以下は最低限の新基準です。
- 原価を下回らない価格設定
- 工程・体制に見合う工期の設定
- リスク情報の共有と契約書への記載
現場管理—安全・品質・生産性を同時に高める「三領域の統合運用」へ
改正後の現場管理では、以下の3つの領域を密接に組み合わせて運用することが求められます。
- 労務管理
労務費基準を守り、適正な賃金や労働条件、福利厚生を確保することで、人材の定着と意欲向上を図る。 - リスク管理
安全管理や工事リスクの事前共有、変更点やヒヤリ・不適合情報を日々発信し、現場トラブルの未然防止と品質保持を両立する。 - デジタル技術活用
ICTツールを活用した日報・進捗・写真・図面の一元管理で、工程管理や是正対応を効率化し、生産性向上を実現する。
これら3領域の管理を同時進行で強化することで「安全・品質・生産性」の全てを底上げできる体制づくりが改正の狙いです。
すぐに着手する3ステップ—2025年を追随から先行へ
施工業者が2025年の改正に対応するためには、早急に準備を進めることが求められます。改正内容を理解し、迅速に行動を起こしましょう。
- 改正内容の理解と社内共有
経営・現場・法務が同じ前提で議論できる資料の統一。 - 契約書式の見直し
原価割れ・短工期の抑止条項、価格変動条項、リスク共有条項をレビュー。 - 現場管理の効率化
ICTツールで日報・出来高・図面・写真・是正を一元管理。
改正対応チェックリスト—抜け漏れ防止に
改正施行までに取り組むべき対応項目をチェックリストとしてまとめました。これに沿って準備を進め、トラブルを防ぎましょう。
- 社内教育:改正ポイントの周知とテスト
- 契約書:原価割れや短工期を防ぐ条項・運用の整備
- 現場体制:労務費やリスク情報のルール化と教育
- ICT導入:出来高・図面・写真・是正の一元管理
改正は負担ではなく、採算性や安全、品質を底上げする仕組みづくりのチャンスです。日付を起点に逆算し、契約・現場・教育を同時並行で整えるほど、スムーズな移行が可能になります。
今すぐ動けば、2025年末の全面施行時には守りの対応から選ばれる体制へ踏み出せます。今すぐ準備を始め、改正をチャンスに変えましょう。

