
建設業のクラウドサービスとは?活用例からメリット、選定のポイントまで解説
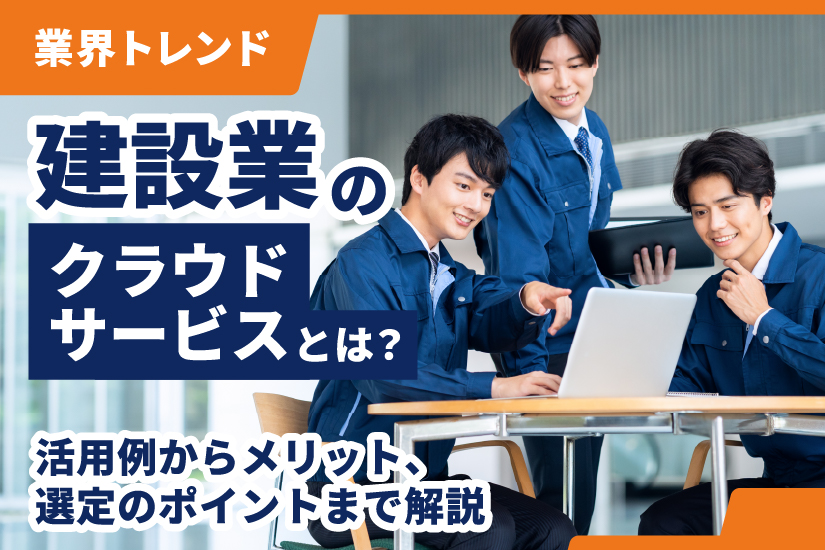
建設業のクラウドサービスとは、建設業に特化した機能を備えたクラウド型の管理システムのことで、工事写真や図面の共有、進捗管理などを効率的に行えるのが特長です。
今回は、建設業におけるクラウドサービスの必要性をはじめ、現場での活用例や導入によるメリット、さらに選定や導入時のポイントまでを詳しく解説します。

建設業のクラウドサービスとは?
建設業向けのクラウドサービスとは、プロジェクトの管理をはじめ、図面や契約書、工事写真の共有、原価や勤怠の管理など、建設業務に特化した機能を備えたクラウド型の管理システムを指します。
自社のパソコンやサーバーに依存せず、インターネット経由でソフトウェアやデータを使えるため、場所を問わず情報にアクセスでき業務の柔軟性が向上します。
建設業の課題に応えるクラウドの必要性
国土交通省は2016年から「i-Construction」を掲げ、デジタル技術による建設現場の自動化を進めています。*1
これは人口減少が進む中でも安全で快適な職場環境を保ちつつ、生産性を高めるための施策です。さらに2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、長時間労働の是正が急務となりました。*2
こうした課題を抱える業界において、クラウドは人手不足・高齢化・過酷な労働環境を改善する基盤ツールとして、その普及が国を挙げて進められています。
なお、総務省が発表した「令和6年通信利用動向調査」によれば、建設業におけるクラウドサービスの導入率はすでに87.0%に達しており、*3今後さらなる拡大が見込まれます。
建設業界の働き方改革と生産性向上を同時に実現するためにも、クラウド導入は避けて通れないステップと言えるでしょう。
建設現場におけるクラウドの活用例

クラウドサービスを導入すると、建設現場のさまざまな業務を効率化できます。
ここでは、建設現場におけるクラウドの活用例を紹介します。
写真・図面・書類の共有をクラウドでスムーズに
クラウドを活用すれば、遠隔地にいても、現場の状況をリアルタイムの映像や写真で視覚的に確認しながら、円滑なコミュニケーションがとれます。
例えば、タブレットで撮影した写真や動画をリアルタイム共有すれば、本社や事務所側も即座に状況を把握できるため判断が早まり、施工もスムーズに進みます。
さらに、図面の修正はクラウド上で共同編集でき、履歴を残しながらスピーディーに対応可能です。
工程や進捗管理をクラウドで「見える化」
工程表や進捗をクラウドで一元管理することで、常に最新状況を見える化できます。
プロジェクト管理機能を使えば、担当者ごとのタスク割り当ても容易で、進捗状況が一目瞭然です。
予定通りに進んでいるかを即座に確認できるほか、遅延の兆候があれば自動アラートで早期対応につなげられます。
日報・報告・連絡のやり取りを効率化
日報や各種報告をクラウドに集約すれば、現場と事務所間のやり取りがよりスムーズになります。
チャット機能を使えば、スタンプなどで即座に意思表示でき、メールのような堅苦しい形式に縛られません。その結果、意思決定のスピードが大幅に向上します。
見積・発注管理もクラウドで一元化
見積や発注業務をクラウドで一元管理すれば、書類作成から保存までワンストップで完結します。
すべてのデータがオンラインに残るため発注状況をひと目で把握でき、滞留があればすぐにフォローが可能です。
見積書・請求書・発注書・納品書もオンラインで同時確認・承認できるため、承認フローの短縮につながります。

建設業におけるクラウド導入のメリット
ここでは、建設業においてクラウドサービスを導入するメリットを紹介します。
生産性が上がり、残業時間を削減できる
クラウドを利用すれば生産性が上がり残業時間を削減できるため、少人数でも現場を回せる体制が整い、人手不足対策にも効果的です。
資材搬入伝票や手書きの使用記録などをクラウド上で管理し、自動で集計・計算ができるようになるため、データ入力といった重複作業が減ります。
さらに、紙で管理していた資料もクラウドに保存すれば、検索や閲覧がその場で即座にできるため、資料探しや保管庫への移動にかかっていた時間を削減できます。
コストが削減され、経営状態が改善する
クラウドの使用で業務の効率化とともにコスト削減が可能になり、経営状態の改善につながります。
例えば、紙の図面をPDF化しクラウド上で共有すれば、印刷にかかる紙代やトナー代を削減可能です。
さらに、クラウド上では経費の使用状況を項目別に素早く把握できるため、支出の多い部分や無駄を見つけやすくなります。これにより、的確なコスト管理が行え、経営の健全化が図れます。
情報共有がスムーズになる
クラウドを活用すれば、現場と事務所をはじめ関係者全員が同じ情報をリアルタイムで共有でき、業務の遂行や意思疎通が格段にスピードアップします。
かつて電話やFAXに頼っていた頃は、情報の行き違いで後から重大なミスが発覚するリスクがありました。
しかし、クラウド上のやり取りは履歴が自動で残るため、透明性が高く、こうしたトラブルを未然に防げます。
安全対策を強化できる
ヒヤリハットの報告や作業中に注意するべきこと、危険個所、機械の扱い方などをクラウド上に蓄積すれば、従業員が現場でいつでも確認でき、安全対策を強化できます。
また、過去の事故やヒヤリハットの情報を蓄積すれば、それらを項目ごとに分類したり、傾向を分析したりして再発防止策を立てることも可能です。
クラウドを導入する際のポイント
ここでは、クラウドサービスの導入を成功させるために、事前に確認しておきたい選定のポイントや、導入までの実施手順を紹介します。
導入目的と必要な機能を明らかにする
最も効果的なクラウドサービスを導入するためには、最初に自社の業務プロセスとそのプロセスに含まれる各タスクを洗い出します。
続いて各タスクで時間がかかっている作業や解決すべき課題を特定し、求められる機能を明らかにします。そのうえで、機能が過不足なく備わったサービスを選定しましょう。
複数ツールの併用を検討する場合もありますが、可能な限り多様な機能を一つに集約し、一元管理できるツールを選ぶことをおすすめします。
情報を一か所に集約できるため、社員にとって管理が簡単で、操作方法も習得しやすいというメリットがあります。
現場での操作性を確認する
選定したクラウドサービスがさまざまな状況下でも使いやすいかどうかを判断するため、必ず実際の現場で操作性を確認しましょう。
試用期間が設けられている場合は積極的に活用し、現場でテストしながら、直感的に操作できる UI/UX か、マニュアルやサポート体制が充実しているかどうかも併せて確認します。
また、導入時には説明会や勉強会を開催し、導入の目的とメリットを訴求して利便性を実感してもらうことで、導入をスムーズに進められます。
コストとROI(投資対効果)を把握する
クラウドの利用には初期費用、月額利用料、オプション料金などが発生します。料金体系を把握したうえで、かかるコストに対してどの程度の ROI が得られるかを事前に確認しましょう。
例えばクラウド導入により削減できる作業時間を試算し、その時間価値を金額換算して ROI を可視化したり、印刷費や交通費など、削減可能な経費を見積もったりすることも有効です。
サービスによっては従量課金制プランを提供している場合もあります。利用状況に応じてコストが変動するため、導入規模や運用形態に合わせて最適なプランを選択しましょう。
データの保護体制を確認する
クラウドを導入する際は、まずサービスが次の基本対策を備えているかを確認しましょう。
- 通信経路の暗号化(TLS など:送受信データを暗号化し盗み見を防ぐ)
- ID/権限管理(ロール設定・操作ログの記録で「誰が何をしたか」を把握)
- 自動バックアップと災害復旧体制(障害や災害時にデータを復元できる仕組み)
特定のIPや時間帯に利用を限定できるアクセス制限機能や、パスワードに加えてスマホ通知や指紋認証などを組み合わせる多要素認証(MFA)・生体認証機能があれば、一層安心です。
さらにこれらの機能を最大限活用するために、社内でセキュリティルールの策定を行い、社内に周知し、万全の体制を整えましょう。
建設業のクラウドを使えばさまざまな課題を解決できる
建設業におけるクラウド活用は、働き方改革への対応やDX推進の切り札としてますます重要性を増しています。
クラウドサービスを導入すれば、現場と本社の情報共有がスムーズになり、生産性向上やコスト削減、安全管理強化など多方面にわたる効果が得られます。
本記事で解説したポイントを参考に、導入の目的と期待する効果を明確にしたうえで、最適なサービスを選定し、クラウドの力で建設業のDXを加速させましょう。
出典:
*1i-Construction 2.0 ~建設現場のオートメーション化に向けて|国土交通省
*2建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省
*3「令和6年通信利用動向調査の結果(概要)|総務省(P24部分)

